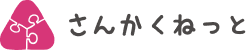数字で見る女性活躍と両立支援
森永製菓の女性活躍推進、仕事と家庭の両立支援の状況などを数字でまとめています。採用、従業員、働き方、キャリア、賃金の内容を、食料品、飲料・たばこ・飼料製造業の平均とともに、それぞれ数字で見てみましょう。
関連トピックス

- 求職者向けトピックス
食料品、飲料・たばこ・飼料製造業には、畜産食料品、水産食料品など、野菜缶詰、果実缶詰、農産保存食料品など、調味料、糖類、動植物油…
採用
採用者の性別割合
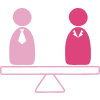
男性
61.9%
女性
38.1%
正社員
まずは業種平均から、採用者の女性割合の傾向を確認したうえで、現在の従業員の男女比も合わせて見てみましょう。上場企業における採用者の女性割合は、全体平均に比べてやや低い傾向にありそうです。
採用での競争倍率
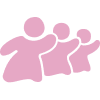
男性
54.4倍
女性
74.9倍
正社員
採用での競争倍率は、人手不足の業種ほど倍率が低くなる傾向にありそうです。一方で、「食料品、飲料・たばこ・飼料製造業」の業種では、性別を問わず、全体平均よりも格段に競争が厳しくなっているようです。
中途採用実績
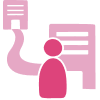
男性
15人
女性
3人
まずは業種平均から、中途採用で性別による傾向があるか確認しましょう。上場企業における中途採用実績は、女性の採用が男性の半分以下となっています。
従業員
従業員数
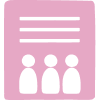
2422人
同業種の中でどの程度の会社規模か確認し、業績等も可能な限り調べておきましょう。
従業員の男女比
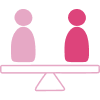
男性
75.7%
女性
24.3%
正社員
上場企業の女性割合が低い傾向にありそうです。ただし、全体的に従業員の男女比よりも高い割合で、女性を採用しているともいえそうです。
平均勤続年数
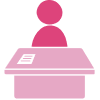
男性
20.2年
女性
15年
正社員
終身雇用の考えはほぼなくなってきていますが、勤続年数の平均から、中長期的なキャリア設計を測る指標として10年定着できる企業かという基準でみてもよさそうです。
働き方
有給休暇取得率
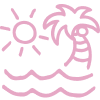
75.8%
正社員
取得率と合わせて、半日単位・時間単位などでの取得や、休暇の申請方法などの実態的な内容も確認しておきましょう。
育児休業取得率
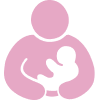
男性
79%
女性
100%
正社員
取得率と合わせて、育児休業から復帰後に、短時間勤務や在宅勤務、フレックスタイムなど柔軟な働き方ができるかも確認しておきましょう。
平均残業時間
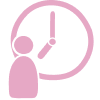
13.1時間/月
対象正社員
数字と合わせて、長時間労働是正のための取り組みや残業の申請方法などの実態的な内容も確認しておきましょう。
キャリア
女性の係長級比率
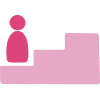
12.7%
ー人/ー人
管理職・役員への女性登用のパイプライン構築のためには、内部人材の採用・育成の強化が必要不可欠です。外部からの採用だけでなく、既存社員へのリーダー育成に対する取り組みも確認するようにしましょう。
女性の管理職比率
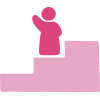
13.4%
ー人/ー人
「管理職」の定義は法律でもやや曖昧で、企業によって定義が異なります。数字を参考にしつつも、フェアな賃金体制、機会の提供、業務の裁量権などの実態を確認するようにしましょう。
女性の役員比率
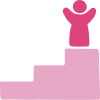
23.1%
ー人/ー人
政府は、プライム市場への上場企業を対象に「2030年までに女性役員の比率を30%以上に」等の数値目標を盛り込み、企業の女性登用を促しています。
賃金
男女の賃金差異(全体)
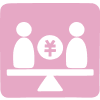
61.5%
男女の賃金差異は、女性の能力や意欲を十分に発揮できないことにつながるため、女性の自立や社会参加を阻害するだけでなく、経済成長や人口減少の対策にも悪影響を及ぼすと考えられます。
男女の賃金差異(正社員)
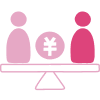
63.9%
日本では女性が子育てや介護を担うことが多く、キャリアの中断や時短勤務が賃金格差の要因にもなっています。柔軟な働き方に関する制度とともに、運用面の実態を把握することが重要となります。
男女の賃金差異(非正規社員)
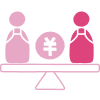
84.3%
一般的に、女性が男性よりも非正規雇用で働く割合が高いことが、賃金格差の原因の一つとされています。また、日本では女性が子育てや介護を担うことが多く、時短勤務が賃金格差の要因となっています。
女性活躍と両立支援の取り組み
女性活躍に関する社内制度の概要
主な施策・制度の詳細は、下記ホームページをご覧ください。
(多様性と活力ある組織づくり)https://www.morinaga.co.jp/company/sustainability/people/diversity.html
仕事と家庭の両立に関する社内制度の概要
主な施策・制度の詳細は、下記ホームページをご覧ください。
(健康で働きやすい労働環境の実現)
https://www.morinaga.co.jp/company/sustainability/people/health-safety.html
長時間労働是正のための取り組み内容
・テレワークの活用(サテライトオフィスの設置)
・コアタイムなしのフルフレックス制度の導入
・パソコンのログオン・ログオフ時間の管理
・一定時間超過者とその上司への警告メール
・長時間労働部署へのヒアリング実施
・計画年休および連続年休取得の促進
・半日単位の有給休暇制度
・会社負担の選択型研修内での労働生産性向上関連セミナーの提供
・労働組合との定期的な情報・意見交換
その他関連する取り組み内容など
・プラチナくるみん認定企業
・2018年より「健康経営優良法人(大規模法人部門)」を8年連続取得
・<2024年度各種制度利用実績>
■年次有給休暇取得率:75.8%
■年次有給休暇平均取得日数:14.0日
■3日以上の連続休暇取得率:93.4%(有給休暇の連続取得奨励)
■男性育児休業取得率 82.9%(準社員を含む)
<女性活躍推進に向けて以下の取り組み・制度を導入>
・育児休業︓子が2歳になるまで無条件で取得可能(最長2歳半まで)
・多様な事由に積み立て休暇を利用可能:子の看護、不妊治療など
・女性特有の健康課題に関する休暇制度(1か月2日を上限とした生理休暇(有給)の付与、妊娠中~出産後1年までの1期間中7日を限度として、1日単位又は半日単位で取得可能な通院つわり休暇の付与)
・育児短時間制度(子が1歳になって初めての4月又は1歳半まで1日4時間以上の勤務または子が中学校就学の始期に達するまで1日6時間以上の勤務)
・本人向け、配偶者向け、上司向けの育休マニュアルの策定・配布による育休者支援
・育休前、保活期間、復職前の上長面談の実施による定期フォロー
・育休期間中希望者への自己啓発(通信教育)補助
<「全員活躍推進」に向けて以下の取り組み・制度を導入>
・再雇用制度(エンゼルリターン制度)
退職した正規従業員のうち、改めて会社で活躍できる状態になった者を再雇用する制度(条件あり)
・勤務地限定制度(NR制度)
出産、育児、介護などの事由に応じ、全国転勤職⇔地域限定職の選択が可能
・2023年4月 副業解禁(一定条件あり)
・コンプライアンス規程・公正取引順守マニュアル・ハラスメントガイドラインの策定
・療養見舞金制度(私傷病により休業した場合、勤続年数に応じ、最大30か月見舞金を支給する)
・勤務時間インターバル規制制度の導入(条件あり/最大11時間)
・キャリア相談室の常設化並びにキャリア自律に関する対話会の実施により、従業員が自身のキャリアについて考える機会を拡大
・働き続けながら子育てを行う社員がキャリア形成を進めていくために休職者制度の変更及び周知
<その他多数研修・セミナーの開催>
・女性社員向けフォーラム
(ダイバーシティフォーラム、女性の健康セミナー、女性従業員向けキャリアセミナー)
・「部下を持つ職位者」を対象に育成力強化研修
・全従業員向けのセルフケアセミナー・ラインケアセミナー
・ダイバーシティ研修、アンコンシャスバイアス研修、コンプライアンス研修
・全従業員向け/管理職向け介護セミナー実施
・キャリア支援力強化にむけて30代を対象としたワークショップを実施 等
【参考】社内制度の導入割合と業種の特徴
職種・雇用形態転換制度
在宅勤務・テレワーク
正社員再雇用・中途採用制度
短時間勤務制度
教育訓練・研修制度
病気・不妊治療休暇
キャリアコンサルティング制度
年次有給休暇時間単位取得制度
フレックスタイム制度
「食料品製造業」、「飲料・たばこ・飼料製造業」は、安全で高品質な製品を安定供給する社会的に重要な産業です。HACCPなどの衛生管理、AI・IoTを活用した自動化、健康志向やサステナビリティ対応が求められています。シフト制勤務が一般的で、製造・品質管理・商品開発・生産管理など幅広い職種があります。海外市場やエコ包装対応など国際的な取り組みも拡大中で、チーム連携や改善提案を通じてキャリアを築ける分野です。