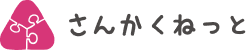数字で見る女性活躍と両立支援
中外製薬の女性活躍推進、仕事と家庭の両立支援の状況などを数字でまとめています。採用、従業員、働き方、キャリア、賃金の内容を、化学工業の平均とともに、それぞれ数字で見てみましょう。
関連トピックス

- 求職者向けトピックス
化学工業には、化学的処理を主な製造過程とする事業及びこれらの化学的処理によって得られた物質の混合、又は最終処理を行う事業のうち他…
採用
採用者の性別割合
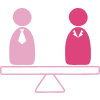
男性
55.9%
女性
44.1%
新卒(うち女性63/143人)
まずは業種平均から、採用者の女性割合の傾向を確認したうえで、現在の従業員の男女比も合わせて見てみましょう。上場企業における採用者の女性割合は、全体平均に比べてやや低い傾向にありそうです。
採用での競争倍率
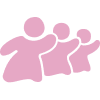
男性
ー倍
女性
ー倍
採用での競争倍率は、人手不足の業種ほど倍率が低くなる傾向にありそうです。一方で、「化学工業」の業種では、性別を問わず、全体平均よりも格段に競争が厳しくなっているようです。
中途採用実績
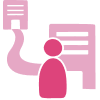
男性
91人
女性
38人
まずは業種平均から、中途採用で性別による傾向があるか確認しましょう。上場企業における中途採用実績は、女性の採用が男性の半分以下となっています。
従業員
従業員数
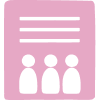
5103人
同業種の中でどの程度の会社規模か確認し、業績等も可能な限り調べておきましょう。
従業員の男女比
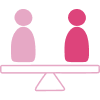
男性
66.4%
女性
33.6%
正社員
上場企業の女性割合が低い傾向にありそうです。ただし、全体的に従業員の男女比よりも高い割合で、女性を採用しているともいえそうです。
平均勤続年数
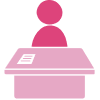
男性
14.9年
女性
12.2年
正社員
終身雇用の考えはほぼなくなってきていますが、勤続年数の平均から、中長期的なキャリア設計を測る指標として10年定着できる企業かという基準でみてもよさそうです。
働き方
有給休暇取得率
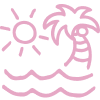
66%
正社員
「化学工業」の業種平均の有給休暇取得率は、全体平均よりも高くなっています。取得率と合わせて、半日単位・時間単位などでの取得や、休暇の申請方法などの実態的な内容も確認しておきましょう。
育児休業取得率
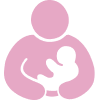
男性
87.6%
女性
100%
正社員
「化学工業」の業種平均の育児休業取得率(男性)は、全体平均よりも高くなっています。取得率と合わせて、育児休業から復帰後に、短時間勤務や在宅勤務、フレックスタイムなど柔軟な働き方ができるかも確認しておきましょう。
平均残業時間
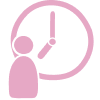
4時間/月
対象正社員
数字と合わせて、長時間労働是正のための取り組みや残業の申請方法などの実態的な内容も確認しておきましょう。
キャリア
女性の係長級比率
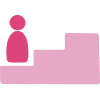
29.4%
262人/892人
管理職・役員への女性登用のパイプライン構築のためには、内部人材の採用・育成の強化が必要不可欠です。外部からの採用だけでなく、既存社員へのリーダー育成に対する取り組みも確認するようにしましょう。
女性の管理職比率
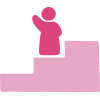
19%
266人/1401人
「管理職」の定義は法律でもやや曖昧で、企業によって定義が異なります。数字を参考にしつつも、フェアな賃金体制、機会の提供、業務の裁量権などの実態を確認するようにしましょう。
女性の役員比率
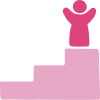
28.6%
4人/14人
政府は、プライム市場への上場企業を対象に「2030年までに女性役員の比率を30%以上に」等の数値目標を盛り込み、企業の女性登用を促しています。
賃金
男女の賃金差異(全体)
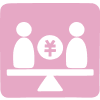
78.7%
男女の賃金差異は、女性の能力や意欲を十分に発揮できないことにつながるため、女性の自立や社会参加を阻害するだけでなく、経済成長や人口減少の対策にも悪影響を及ぼすと考えられます。
男女の賃金差異(正社員)
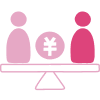
78.6%
日本では女性が子育てや介護を担うことが多く、キャリアの中断や時短勤務が賃金格差の要因にもなっています。柔軟な働き方に関する制度とともに、運用面の実態を把握することが重要となります。
男女の賃金差異(非正規社員)
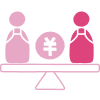
70.6%
一般的に、女性が男性よりも非正規雇用で働く割合が高いことが、賃金格差の原因の一つとされています。また、日本では女性が子育てや介護を担うことが多く、時短勤務が賃金格差の要因となっています。
女性活躍と両立支援の取り組み
女性活躍に関する社内制度の概要
●時短勤務者の上司を対象に中長期でのキャリア形成の意義や部下への機会提供を後押しする研修実施
●D&I推進のキーパーソンとなるマネジャー全員を対象とし、無意識バイアスのe-ラーニングを実施
●産前・産後の上司・部下間のキャリア面談の実施や面接シートの作成・活用、復職後のキャリア形成に向けた上司・部下を対象としたe-ラーニングの実施
●従業員の自律的な成長・キャリア形成支援を目的とした上司・部下の対話を強化する施策としてCheck in(1on1)を導入
●全従業員を対象にハラスメント防?に関する法律の改正点を理解する研修を実施
●女性の自発的なキャリア形成の支援を目的とした選抜式研修を毎年実施
●全マネジャーを対象した部下への成長支援を目的としたフィードバック研修を実施
●中長期的なキャリア形成の支援を目的とした自身のキャリアを考えるイベント開催
●年齢・属性にかかわらずチャレンジを後押しする?事制度の導入(個々?の能?や過去の貢献、ライフイベント等により一時的に業務に制限がかかる従業員等に関わらず公正に評価(直属上司だけでなく、複数の評価者による客観的な意見を取り入れる仕組みを運用)し、昇格・昇給の機会を提供)
仕事と家庭の両立に関する社内制度の概要
●配偶者出産休暇:2日(有給)
●子の看護休暇:年間10日(無給/小学校就学前の子女の病気等の看護)
●妊産婦の通院休暇:妊娠期間に応じて一定日数付与(有給)
●生理休暇:2日(有給)
●保活コンシェルジュの導入(保育環境の整備支援による早期復帰の支援)
●がんに関する就労支援ハンドブックの作成・展開
●介護リテラシーに関する学びの機会の提供(自己診断ツール、メルマガ配信、e-ラーニング、オンラインセミナー、相談デー)
●MR配偶者同居サポートプラン
●?の保育所など送迎時における営業?両の利?
長時間労働是正のための取り組み内容
2018年より「仕事の効率性」「働き方の柔軟性」「コミュニケーション活性化」に焦点を当てて進めていた「働き方改革」を発展的に拡大し、2021年より、社員の働き方だけでなく、働くことに対する内発的動機付けを高めるための新たな改革として「働きがい改革」よりスタート。「働きがい改革」では、「社員エンゲージメント」と「社員が活きる環境(従来の働き方改革の取り組みを含む)」を取り組みを通じて、多様な社員の働きがいを高めることを目指して取り組みを進めている。「社員が活きる環境」では、多様な社員が自律的に働き方を選択できる環境整備として、より柔軟性の高い働き方となる働く場所に捉われない働き方(遠隔地テレワーク、フルリモート勤務、モバイル勤務等)の各種制度を導入している。
【制度・仕組み】
・テレワーク勤務制度(勤務場所:在宅およびサテライトオフィス、利用回数:出社勤務の方針やルールは組織毎に自律的に設定)
・モバイル勤務:テレワーク勤務のうち、在宅勤務やサテライトオフィス以外の場所で就労を可能とする働き方の導入
(移動 の合間のカフェ等での仕事や、 旅行先等で限られた時間、仕事を行うこと(ワーケーション)も可能となる)
・遠隔地テレワーク勤務:社員が居住地と隣接する(通勤可能圏)の在勤事業所で働くことができる制度
・フルリモート勤務制度:在勤事業所への通勤が困難な遠隔地(通勤可能圏外)に居住し、テレワーク勤務で業務に支障のない社員(育児、介護以外に治療等の理由がある)について、事業所勤務を前提としないテレワークを主体とする働き方を可能とする制度
・スーパーフレックスタイム制度(コアタイムなし、フレキシブルタイム:5-22時)
・半日単位および時間単位有給休暇
・有給休暇取得奨励日の設定(全社共通で年間5日設定。極力4連休となるよう指定)
・時間外・休日・深夜労働の制限または免除(育児・介護等)
【労働時間・有給休暇取得の実績管理】
・全社および部門別の時間外労働および有給休暇取得の実績について、中央および事業所労使協議会で共有・議論し、従業員に広報を通じて周知
・長時間労働者の本人・上司へのメール発信による業務面での改善指示や本人の健康面でのフォロー実施(産業医面談の推奨等)
・定期的なミニサーベイ(3ヵ月に1回)により、社員の長時間労働や仕事量の負荷を把握し、その結果をもとに上司との面談(毎月の1on1)でフォローを実施
【働きがい改革】
・管理職のマネジメントスキルを高める取り組みとして、マネジャーに労務管理の観点で必要な労働時間管理等に関わる知識等を案内し、マネジャーを通じた部下への周知、および職場内で労働時間に対する意識啓発(長時間労働改善も含む)の機会の設定
・テレワーク勤務を活用した柔軟な働き方の定着に向けて職場・組織単位でのワークショップや対話を実施(個人と組織の生産性向上・効率化やコミュニケーション活性化の観点で対話等)
・働き方の自由度を更に高め、女性も含めた多様な社員が自律的に働き方を選択し、キャリアを断念することなく働き続けながら活躍できる環境整備を進めるべく、働く場所に捉われない働き方を実現する環境整備(上記の【制度・仕組み】を参照)
・従業員のセルフマネジメントの意識向上を目的として全社員に向けた働き方に関するメルマガ配信の実施
・業務配分や業務の棚卸、デジタル活用による効率化・業務削減、労働時間削減をテーマとしたディスカッションを本部単位で実施
・働き方を含めた働きがいに関する意識調査アンケートを実施し、生産性や効率性の観点での各部門の実態を把握し、部門毎の主体的な取り組みを支援
・Microsoft Analysisの導入(一人ひとりの働き方の分析・改善のサポートツール)
その他関連する取り組み内容など
●D&Iを経営課題の重要な⼀つとして位置づけており、多様性はイノベーションには⽋かせないものと考え、
2012年からは専任組織(人事部ダイバーシティ推進室)を設置し、女性の仕事との両立支援や活躍支援も含めたD&Iに関わる取り組みを実施
●経営層や部門長を巻き込んだダイバーシティ&インクルージョンの全社の推進イベントとして企画・実行している「中外ダイバーシティDAYS」等を通じて社員一人ひとりが理解を深め、行動を変えていく後押しを行っている。2023年は柔軟な働き方を行っていく上で重要となるコミュニケーションをテーマに、多様性を活かし合うためのコミュニケーションの在り方について経営層も交えてトークセッション等を実施。また、社員を対象としたアンコンシャスバイアスの理解を深めるセミナーや女性の健康問題等の職場内のリテラシーを高めるセミナーを継続実施(年1回開催)
●女性活躍推進における経営層や部門長のコミットメントとして、毎年以下の活動を実施
・女性活躍の重要性や意義に関し、年頭所信やダイバーシティのイベントで経営トップからメッセージ発信
・女性マネジャーの発掘・育成・登用の加速に向け、部門長および担当役員がコミットした上で部門別にKPIを設定
・毎年1度経営トップ以下担当役員出席の下、育成や登用状況の進捗確認とKPI達成に向けた課題や打ち手について議論
・タレントマネジメントにおけるキーポジション(部長クラス)の後継候補者に女性を必ずノミネート
●女性リーダー・マネジャー候補者の上司を対象に、女性活躍の意義や部下育成をテーマとした研修を毎年実施
●新規に管理職として登用した人数実績(女性の割合):32.3%
●主体的なキャリア形成の機会として、契約社員から正社員への転採用制度、一定基準を満たした場合に兼業・副業を認める仕組み、
全部署を対象とした社内公募制、社外公募制(一定年齢以上)、社内インターンシップ、フレキシブルキャリア休職(会社に在籍しながら学位や資格を取得するために休職を可能とする)、ボランティア休暇、留職プログラムを導入
【参考】社内制度の導入割合と業種の特徴
職種・雇用形態転換制度
在宅勤務・テレワーク
正社員再雇用・中途採用制度
短時間勤務制度
教育訓練・研修制度
病気・不妊治療休暇
キャリアコンサルティング制度
年次有給休暇時間単位取得制度
フレックスタイム制度
「化学工業」は、医薬品や化粧品、合成樹脂、肥料など多様な製品を化学反応により生産する産業で、製造管理・研究開発・環境安全といった幅広いキャリアがあります。自動化・技術革新が進む中、高度な装置操作や反応制御スキルが求められます。24時間稼働の現場ではシフト勤務も多く、安全管理と体力が重要です。サステナブルな素材開発や省エネ設備の導入も進んでおり、環境対応と技術力を両立できる人材が活躍の場を広げています。