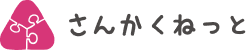数字で見る女性活躍と両立支援
日本航空の女性活躍推進、仕事と家庭の両立支援の状況などを数字でまとめています。採用、従業員、働き方、キャリア、賃金の内容を、運輸業、郵便業の平均とともに、それぞれ数字で見てみましょう。
関連トピックス

- 求職者向けトピックス
運輸業、郵便業には、鉄道、自動車、船舶、航空機又はその他の運送用具による旅客、貨物の運送業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業を営…
採用
採用者の性別割合
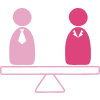
男性
62.3%
女性
37.7%
業務企画職(総合職)
まずは業種平均から、採用者の女性割合の傾向を確認したうえで、現在の従業員の男女比も合わせて見てみましょう。上場企業における採用者の女性割合は、全体平均に比べてやや低い傾向にありそうです。
採用での競争倍率
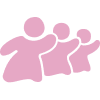
男性
41.4倍
女性
41.4倍
業務企画職(総合職)
採用での競争倍率は、人手不足の業種ほど倍率が低くなる傾向にありそうです。一方で、上場企業では全体平均よりも格段に競争が厳しく、また、女性の競争倍率が男性よりも高くなっているようです。
中途採用実績
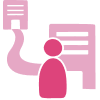
男性
94人
女性
314人
まずは業種平均から、中途採用で性別による傾向があるか確認しましょう。上場企業における中途採用実績は、女性の採用が男性の半分以下となっています。
従業員
従業員数
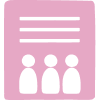
14171人
同業種の中でどの程度の会社規模か確認し、業績等も可能な限り調べておきましょう。
従業員の男女比
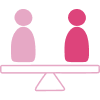
男性
68.6%
女性
31.4%
業務企画職(総合職)
「運輸業、郵便業」の業種は、全体平均と比較して、従業員の女性割合が低い傾向にありそうです。ただし、平均としては、従業員の男女比よりも高い割合で、女性を採用しているともいえそうです。
平均勤続年数
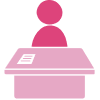
男性
20.5年
女性
15.3年
業務企画職(総合職)
終身雇用の考えはほぼなくなってきていますが、勤続年数の平均から、中長期的なキャリア設計を測る指標として10年定着できる企業かという基準でみてもよさそうです。
働き方
有給休暇取得率
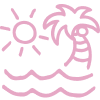
80.0%
全職種
取得率と合わせて、半日単位・時間単位などでの取得や、休暇の申請方法などの実態的な内容も確認しておきましょう。
育児休業取得率
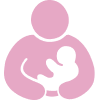
男性
87.5%
女性
100%
全職種
取得率と合わせて、育児休業から復帰後に、短時間勤務や在宅勤務、フレックスタイムなど柔軟な働き方ができるかも確認しておきましょう。
平均残業時間
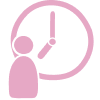
10.2時間/月
基幹的な職種
数字と合わせて、長時間労働是正のための取り組みや残業の申請方法などの実態的な内容も確認しておきましょう。
キャリア
女性の係長級比率
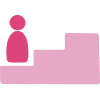
48.4%
1407人/2910人
管理職・役員への女性登用のパイプライン構築のためには、内部人材の採用・育成の強化が必要不可欠です。外部からの採用だけでなく、既存社員へのリーダー育成に対する取り組みも確認するようにしましょう。
女性の管理職比率
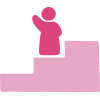
24.2%
299人/1234人
「管理職」の定義は法律でもやや曖昧で、企業によって定義が異なります。数字を参考にしつつも、フェアな賃金体制、機会の提供、業務の裁量権などの実態を確認するようにしましょう。
女性の役員比率
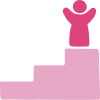
22.9%
8人/35人
政府は、プライム市場への上場企業を対象に「2030年までに女性役員の比率を30%以上に」等の数値目標を盛り込み、企業の女性登用を促しています。
賃金
男女の賃金差異(全体)
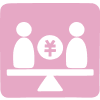
50.3%
男女の賃金差異は、女性の能力や意欲を十分に発揮できないことにつながるため、女性の自立や社会参加を阻害するだけでなく、経済成長や人口減少の対策にも悪影響を及ぼすと考えられます。
男女の賃金差異(正社員)
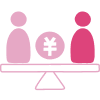
48.9%
日本では女性が子育てや介護を担うことが多く、キャリアの中断や時短勤務が賃金格差の要因にもなっています。柔軟な働き方に関する制度とともに、運用面の実態を把握することが重要となります。
男女の賃金差異(非正規社員)
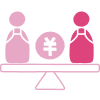
50.2%
一般的に、女性が男性よりも非正規雇用で働く割合が高いことが、賃金格差の原因の一つとされています。また、日本では女性が子育てや介護を担うことが多く、時短勤務が賃金格差の要因となっています。
女性活躍と両立支援の取り組み
経営目標として、JALグループの女性管理職比率30%の達成を掲げており、2024年度末時点で31.5%の進捗となっている。
両立支援制度の整備や多様な働き方を認め、自律的なキャリア形成支援を通して、社員一人ひとりが性別や背景を問わず活躍できる会社づくりを目指している。
女性活躍に関する社内制度の概要
■正社員再雇用
複数の職種にて、キャリアリターン採用を実施。(業務企画職・パイロット職・客室乗務職)
他のフィールドで活躍した元社員を即戦力人財として採用している。
■教育訓練・研修制度
・「JALCAREER」によるキャリアサポート
国家資格を持つ社員が社内キャリアコンサルタントとして、社員の自律的なキャリア形成をサポートし、自ら描くキャリアを実現しながら、やりがいをもって働き続けられるサポートを実施。
・世代別のキャリア研修や選抜の研修のほか、一時的他部署の業務を経験できる「自律的キャリア研修」を実施し、自ら望むキャリアの模索と実現に向け支援を実施。
また、立候補型人事や公募人事のポストも拡大し、自律的にキャリアを描ける環境を整えている。
・社外ネットワークを構築しながら視野を広げ、女性リーダーを育成することを目的に、2005年より「J-Win」、2014年より「21世紀職業財団」の女性リーダー育成研修にに社員を派遣している。
・グループ全体でダイバーシティの推進を行うことを目的と、2015年9月から組織横断プロジェクトとして「JALなでしこラボ」を立ち上げ、2019年11月からは名称を変更し、女性をはじめとする多様な人財の活躍を促進する施策を検討する「JAL D&Iラボ」として活動を継続している。2024年度より「JAL DEIラボ」に名称を変更した。
■ライフイベントに配慮した評価制度
・2022年度より、産前・育児・介護を理由として休職する場合、評価において、1年間は在籍期間に算入しとみなし評価とする制度を導入した。ライフイベントによる昇格遅れが生じにくくなる制度を整えている。
・人財制度の見直しにより、2024年度から年功序列を廃し、能力に応じた登用が可能となった。それにより女性を含む若手社員の早期管理職登用が促進されている。
■女性の健康課題支援
・フェムテックの活用による女性の健康課題支援を行い、月経・更年期を対象としたオンライン診療プログラムを導入している。
女性の健康課題へのサポートを実施。オンラインによる通院の負担軽減に加え、一部費用を会社負担とすることで経済的にもサポートを行っている。
仕事と家庭の両立に関する社内制度の概要
■労働時間適正化への取り組み
業務に効率的に取り組むことで生み出された時間を、社外での経験や自己啓発、心身のリフレッシュに充て、その経験・価値を社内に還元することが企業の成長につながると考えている。
そのため、社内に業務プロセス改革に関する専用相談窓口を設け、各組織における業務効率化を図るなどの取り組みを実施。
年次有給休暇の計画的な取得とあわせ、労働時間の適正化を図っている。
■多様な働き方による自律的な働き方
・フレックスタイム制度
1日1時間以上の勤務とし、日々の労働時間を自ら決めることができる制度。
フレックスタイム制度の清算期間内で所定労働時間分を就労し、労働時間の調整を行うことが可能。
2019年度の法改正で清算期間を3カ月まで延長することが可能となった当制度をいち早く導入している。
・テレワーク(在宅勤務)制度
業務効率と生産性向上を目的とし、オフィス以外の場所で業務を行うことができる制度。通勤時間や移動時間の削減にも繋げている。
・フリーアドレス制度
固定席、固定電話を廃止し、自由にその日の座席を選択できる制度です。
・ワーケーション制度
旅行や帰省時の休暇の取得期間を長くするために、一部の業務を旅先でも認める制度。
2017年度より導入し、旅行や帰省の計画を事前に立てやすくすることや業務の都合で直前に旅程変更する必要をなくすことだけでなく、その土地でしか経験できない体験をすることで自己成長やその後の業務への活力にも繋げている。
・ブリージャー制度
2019年度に導入した出張先で休暇を取得できる制度。休暇の取得促進だけでなく、業務だからこそ訪れた土地での出会いや体験から、自己成長やその後の業務への活力に繋げている。
■出産育児に関する両立支援制度
・育児のための短時間勤務※職種により適用条件が異なります。
小学校3年生までの子を持つ社員が希望に応じて、勤務時間を短くすることが可能。(実働6時間)
・1日単位の深夜業免除措置希望日申請制度 ※客室乗務職
深夜業免除措置を適用中、月間のスケジュールにおいて、1日単位で深夜業を免除する希望日を選択できます。深夜業免除措置を適用しながら、選択した希望日に宿泊を伴う乗務をすることが可能。
・深夜業免除措置※全職種
小学校就学前の子を養育する場合または要介護状態にある対象家族を介護する場合、深夜勤務を免除することが可能。
・産前休職制度※全職種
妊娠後、本人の希望に基づいて産前休職を取得できる。
・出産特別休暇※全職種
出産のため、産前10週、産後10週まで休暇を取得できる。
・出生休暇※全職種
子の出生日の前後2週間以内に、3日間の休暇が取得できる。
・育児休暇※全職種
育児休職とは別に、子の出生日から10週間を限度として任意の日付で休暇が取得できる。
・育児休職制度※全職種
出生日以降、最長で子が満3歳に達する月の月末まで取得可能。
・妊娠中の乗務制度※パイロット
健康状態を慎重に判断し、航空業務に支障のないことを確認した上で、妊娠第13週から第26週の女性運航乗務員は乗務に就くことができる。
・産前地上勤務制度※パイロット・客室乗務職
妊娠後、出産特別休暇取得までの間、地上勤務に就ける制度。
・短日数勤務制度※パイロット・客室乗務職
小学3年生までの子を持つ社員・要介護状態にある家族の介護を担う社員・満50歳に達している社員が希望に応じて、月間の勤務日数を「6割勤務」「8割勤務」「9割勤務」から選択することが可能。
なお、事由により選択できる勤務割合が異なる。(※職種によって対象となる事由が異なります)
・子育てサポート休暇※パイロット・客室乗務職
小学校就学前の子をもつ社員を対象に、月間1日、年10日取得が可能。(取得不可期間あり)
子の養育するのに資する目的であれば利用可能。
・子の看護等のための休暇制度※全職種
小学校3学年修了前の子が、負傷または疾病にかかった場合の世話、あるいは予防接種または健康診断を受けさせるために取得が可能。
感染症による休校、入園式(入学式)、卒園式にも利用可能。
取得日数は年間5日間、対象となる子が2人以上いるときは年間10日間の取得が可能。
・配偶者転勤同行休職制度※全職種
小学校就学前の子を養育する社員が、配偶者の転勤による転居に伴い、その配偶者に同行し転居先において生活を共にすることにより通勤が困難となる場合に、最大3年間休職が可能。
海外赴任の場合は、子の有無を問わない。
・不妊治療休職制度※全職種
社員が高度な不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けるために、最大1年間休職が可能。
■介護に関する両立支援制度
・介護休暇※全職種
被介護者の介護、その他の世話のため、年間5日(被介護者2名以上の場合は年間10日)まで取得が可能。
・介護休職制度※全職種
同一の被介護者が一つの負傷、疾病などにより、要介護状態に至った場合に3回まで取得が可能。(通算での取得期間の制限あり)
長時間労働是正のための取り組み内容
客観的データとしてのパソコンのログデータを活用した労働時間管理を実施しているほか、「勤務実績報告会」で全部門・全社員の時間外労働時間、年休取得等のデータを見える化している。
加えて、各部門長による課題の深堀と改善策を全部門で共有し、優れた取組を迅速に他部門に展開できる素地を作っています。
【これまでの取り組み】
○働き方の見直しを全社横断的に推進するため、2014年12月に「ワークスタイル変革推進室」を新設。
同室が中心となり、約5,000名を対象に働き方を考えるきっかけをつくる「スタートアップワークショップ」や必要なスキルを身に付ける「スキルアップワークショップ」を3回開催。
○更に2017年6月に既存の「ワークスタイル変革推進室」と「ダイバーシティ推進室」を人財戦略部の下にグループとして集約し、ダイバーシティとワークスタイル変革を一体となって促進する体制を整備。
ダイバーシティが重要な経営戦略であることを明確に位置付けています。
〇出社とテレワークのそれぞれのメリットを最大限に活かすために、ハイブリッドワークガイドラインを策定しました。働き方に関する全社ルールを掲載し、全社員に周知しています。
〇グループ全社員に対し、DX教育を開始しました。業務の見直しを図り、生産性を向上させるための教育を展開しています。
○2017年度から総実労働時間1850時間の目標を掲げ、有給休暇20日(100%)と月平均残業時間4時間の達成に向けて取り組んでおり、時間外労働を実施する場合には所属長への事前申請を徹底しています。
(総実労働時間は2016年度末実績 1,930時間→2024年度末実績 1,875時間)
その他関連する取り組み内容など
■女性登用に関する目標・内容
・JALグループの女性管理職比率30%以上の達成を、経営目標として掲げており、2024年度末時点で31.5%の進捗となっている。
・客室乗務職管理職を営業支社長に登用するなど、出身領域にとらわれず活躍領域の拡大を進め、積極的に女性の登用を進めている。
・フェムテックの活用による女性の健康課題支援を行い、月経・更年期を対象としたオンライン診療プログラムを導入している。
女性の健康課題へのサポートを実施。オンラインによる通院の負担軽減に加え、一部費用を会社負担とすることで経済的にもサポートを行っている。
■ライフイベントに配慮した評価制度
・2022年度より、産前・育児・介護を理由として休職する場合、評価において、1年間は在籍期間に算入しとみなし評価とする制度を導入した。ライフイベントによる昇格遅れが生じにくくなる制度を整えている。
・人財制度の見直しにより、2024年度から年功序列を廃し、能力に応じた登用が可能となった。それにより女性を含む若手社員の早期管理職登用が促進されている。
■男性社員の育児休業の取得奨励
・オンライン父親学級や管理職向けのセミナーを開催し、取得者と上司の双方の意識醸成に務めている。
2023年度には育児休業を取得した社員の座談会なども実施し、男性社員による育児休業の取得事例の共有を進めている。
・「育休計画」の提出を義務化し、上司と確認の場を持つことで気兼ねなく育休を取得できる環境づくりをすすめ、産後10週で2週間以上育休取得を行う社員を50%以上にするという定量目標の達成を目指している。
■キャリア形成・キャリアアップの支援
・「JALCAREER」によるキャリアサポート
国家資格を持つ社員が社内キャリアコンサルタントとして、社員の自律的なキャリア形成をサポートし、自ら描くキャリアを実現しながら、やりがいをもって働き続けられるサポートを実施。
・世代別のキャリア研修や選抜の研修のほか、一時的他部署の業務を経験できる「自律的キャリア研修」を実施し、自ら望むキャリアの模索と実現に向け支援を実施。
また、立候補型人事や公募人事のポストも拡大し、自律的にキャリアを描ける環境を整えている。
・ボランティア活動のための休暇制度があり、また副業・兼業の許可の実績あり。
■2016年に「国連女性のエンパワメント原則(WEPs)」に署名している。
■ベビーシッター補助制度あり
■8年連続「PRIDE指標における最上位のゴールド」を受賞
企業のLGBTQなどのセクシャルマイノリティに関する取り組みを評価する「PRIDE指標2023」において、2016年から8年連続となる最上位の「ゴールド」を受賞。
■「テレワーク先駆者百選」に選出。
■「D&I AWARD 2024」において4年連続となる 最高評価の「ベストワークプレイス」に認定。
また、従業員数3001人以上の企業部門にて、「D&I AWARD賞」を受賞。
■6度目の「健康経営銘柄2024」に選定。
【参考】社内制度の導入割合と業種の特徴
職種・雇用形態転換制度
在宅勤務・テレワーク
正社員再雇用・中途採用制度
短時間勤務制度
教育訓練・研修制度
病気・不妊治療休暇
キャリアコンサルティング制度
年次有給休暇時間単位取得制度
フレックスタイム制度
「運輸業・郵便業」は、陸・海・空の輸送や物流、郵便を通じて社会を支えるインフラ産業です。トラック運転手やパイロット、整備士、配達員など多様な職種があり、正確・安全なサービス提供が求められます。EC拡大により物流の需要が増加し、効率的なシステムやデジタル技術の導入が進んでいます。体力を要する業務やシフト勤務が多く、安全管理や資格取得が重要です。国際物流では語学力も活かせます。人手不足対策として、女性や外国人の活躍、AI・自動化技術の導入も進んでおり、将来性のある業界です。