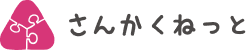数字で見る女性活躍と両立支援
豊田合成の女性活躍推進、仕事と家庭の両立支援の状況などを数字でまとめています。採用、従業員、働き方、キャリア、賃金の内容を、輸送用機械器具製造業の平均とともに、それぞれ数字で見てみましょう。
関連トピックス

- 求職者向けトピックス
輸送用機械器具製造業には、自動車など輸送用機械器具を製造する事業が分類されます。主な製品は、自動車、船舶、航空機、鉄道車両及びそ…
採用
採用者の性別割合
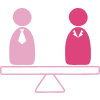
男性
72.8%
女性
27.2%
事技職
まずは業種平均から、採用者の女性割合の傾向を確認したうえで、現在の従業員の男女比も合わせて見てみましょう。上場企業における採用者の女性割合は、全体平均に比べてやや低い傾向にありそうです。
採用での競争倍率
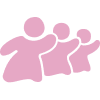
男性
8.2倍
女性
9.8倍
事技職
採用での競争倍率は、人手不足の業種ほど倍率が低くなる傾向にありそうです。一方で、上場企業では全体平均よりも格段に競争が厳しく、また、女性の競争倍率が男性よりも高くなっているようです。
中途採用実績
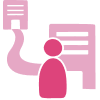
男性
59人
女性
6人
まずは業種平均から、中途採用で性別による傾向があるか確認しましょう。上場企業における中途採用実績は、女性の採用が男性の半分以下となっています。
従業員
従業員数
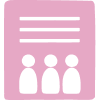
6676人
同業種の中でどの程度の会社規模か確認し、業績等も可能な限り調べておきましょう。
従業員の男女比
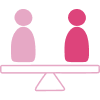
男性
84.9%
女性
15.1%
事技職
「輸送用機械器具製造業」の業種は、全体平均と比較して、従業員の女性割合が低い傾向にありそうです。ただし、平均としては、従業員の男女比よりも高い割合で、女性を採用しているともいえそうです。
平均勤続年数
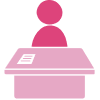
男性
15.1年
女性
16.7年
事技職
終身雇用の考えはほぼなくなってきていますが、勤続年数の平均から、中長期的なキャリア設計を測る指標として10年定着できる企業かという基準でみてもよさそうです。
働き方
有給休暇取得率
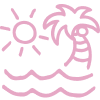
92.8%
事技職
「輸送用機械器具製造業」の業種平均の有給休暇取得率は、全体平均よりも高くなっています。取得率と合わせて、半日単位・時間単位などでの取得や、休暇の申請方法などの実態的な内容も確認しておきましょう。
育児休業取得率
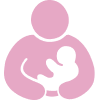
男性
63.6%
女性
116.7%
正社員
取得率と合わせて、育児休業から復帰後に、短時間勤務や在宅勤務、フレックスタイムなど柔軟な働き方ができるかも確認しておきましょう。
平均残業時間
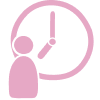
15.2時間/月
対象正社員
数字と合わせて、長時間労働是正のための取り組みや残業の申請方法などの実態的な内容も確認しておきましょう。
キャリア
女性の係長級比率
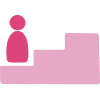
5.5%
32人/587人
管理職・役員への女性登用のパイプライン構築のためには、内部人材の採用・育成の強化が必要不可欠です。外部からの採用だけでなく、既存社員へのリーダー育成に対する取り組みも確認するようにしましょう。
女性の管理職比率
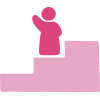
3.6%
41人/1131人
「管理職」の定義は法律でもやや曖昧で、企業によって定義が異なります。数字を参考にしつつも、フェアな賃金体制、機会の提供、業務の裁量権などの実態を確認するようにしましょう。
女性の役員比率
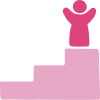
20.0%
3人/15人
政府は、プライム市場への上場企業を対象に「2030年までに女性役員の比率を30%以上に」等の数値目標を盛り込み、企業の女性登用を促しています。
賃金
男女の賃金差異(全体)
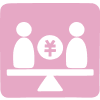
79.1%
男女の賃金差異は、女性の能力や意欲を十分に発揮できないことにつながるため、女性の自立や社会参加を阻害するだけでなく、経済成長や人口減少の対策にも悪影響を及ぼすと考えられます。
男女の賃金差異(正社員)
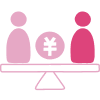
78.4%
日本では女性が子育てや介護を担うことが多く、キャリアの中断や時短勤務が賃金格差の要因にもなっています。柔軟な働き方に関する制度とともに、運用面の実態を把握することが重要となります。
男女の賃金差異(非正規社員)
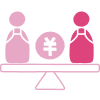
84.9%
一般的に、女性が男性よりも非正規雇用で働く割合が高いことが、賃金格差の原因の一つとされています。また、日本では女性が子育てや介護を担うことが多く、時短勤務が賃金格差の要因となっています。
女性活躍と両立支援の取り組み
性別に関わらず、全従業員が活躍・成長できる状態を実現し、多様性を活かした新たな価値創造へつなげるため、DE&Iの重点取り組みの1つとして、女性活躍推進活動を実施しています。具体的には、「女性従業員の育成・活躍支援」(女性従業員のキャリアアップ、リーダーとしての活躍を後押しする研修・交流会など)・「上司の意識・行動改革」(両立支援セミナー、講演会など)・「仕事と生活の両立支援」(育休・短時間勤務制度の拡充など)の3つを軸に、女性が安心して長く働き、成長し続けられる環境づくりを推進しています。
また、技能職場においても、からくり改善やロボットの活用拡大による高負荷作業の見直しや、トイレ・休憩室の改善など、性別や年齢に関わらず活躍できる製造現場づくりを進め、女性従業員の活躍を後押ししています。
女性活躍に関する社内制度の概要
①育児・介護・配偶者の転勤などのやむを得ない理由で退職する正社員の復職申請制度(カムバック制度)
②配偶者の海外出向に帯同する者の休職制度(海外帯同休職制度)
③近い将来管理職・リーダーを目指す女性従業員を対象とした通年の研修プログラム(アドバンスプログラム、エンカレッジプログラム)
仕事と家庭の両立に関する社内制度の概要
①休業期間の拡大( 育児休業: 2歳になるまで、介護休業: 1年と93日間)
②育児・介護特別勤務免除(育児・介護事由による勤務時間と遅刻・早退・離業の回数カウントを免除する制度。それぞれ80時間/年、無給)
③在宅勤務上限回数緩和(介護・加療事由による場合、申請に基づき10回/月の上限回数を変更可能)
④加療のための短日・短時間勤務(12,15日/月の短日、4・6・7時間の短時間勤務から選択)
⑤産前/産後の特別休暇(産後8週間の特別休暇(無給))
⑥祝日臨時託児所の開設
⑦祝日託児所の利用補助(1日あたり5,000円/人)
⑧配偶者出産時の特別休暇(3日間100%有給)
⑨育児のための短日勤務制度(4時間・6時間・7時間)
⑲介護のための短日勤務制度(4時間・6時間)
⑪加療のための短日・短時間制度(12日/月・15日/月・4時間・6時間・7時間)
長時間労働是正のための取り組み内容
・個人別の労務時間等管理データを毎月配布
・勤怠管理システムの導入による労務状況の高負荷者の見える化
・高負荷者上司への注意喚起
その他関連する取り組み内容など
「女性従業員の育成・活躍支援」
・アドバンスプログラム:次期管理職候補層の女性社員を対象に、管理職昇格に向けた育成課題を明確化し、その解消に向け必要な役割付与や機会提供を行うことで、能力向上を図るプログラム。
・エンカレッジプログラム:中堅女性社員を対象に、年間を通じた研修と職場実践、社内外交流により、自身の持ち味を活かしたリーダー像を描くことで、キャリアアップを後押しするプログラム。
・ハートリンク活動:各工場にて人選された技能職女性リーダーを対象に、研修による問題解決手法の習得や、工場見学・他社交流による職場環境改善・キャリア形成の後押しを目指すプロジェクト活動。
「上司の意識・行動改革」
・人権講演会、ウェルビーイング講演会:役員や管理職を対象に、DE&Iやウェルビーイングの理解浸透活動を実施。
・両立支援セミナー:「誰もが働きやすい職場づくり」の実現に向け、管理監督者を対象に両立支援・フェムテックなどについて理解を深めるセミナーを実施
【参考】社内制度の導入割合と業種の特徴
職種・雇用形態転換制度
在宅勤務・テレワーク
正社員再雇用・中途採用制度
短時間勤務制度
教育訓練・研修制度
病気・不妊治療休暇
キャリアコンサルティング制度
年次有給休暇時間単位取得制度
フレックスタイム制度
「輸送用機械器具製造業」は、自動車・航空機・船舶・鉄道車両などの製造を担い、機械・電子・材料など多分野の技術が求められる産業です。EVや自動運転、軽量素材、AI制御など革新が進む中、設計・製造・品質管理など多彩な職種があります。クリーンエネルギーやグローバルプロジェクトへの対応力も必要で、国際的な連携やITスキルがキャリアの武器に。スマートファクトリー化が進み、自動化技術を活かした成長が期待される分野です。